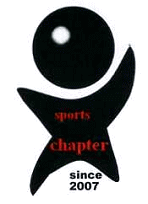膝関節屈曲角度の変化と patellar tendon-tibial angle の関係 ~超音波画像診断装置を用いた膝蓋下脂肪体の移動量の予測~
木下 敬詩 総合理学療法学 Vol.1(2021)pp.3–8
【内容】
膝蓋下脂肪体(以下:IFP)には膝関節の屈曲に伴い近位へ、伸展に伴い膝蓋靭帯と脛骨粗 面近位部との間にウェッジ状に進入し機能的な変形が生じていることが報告されている。 本論文においては超音波画像診断装置(以下;エコー)を用いて膝蓋靭帯と脛骨近位骨端前 面がなす角度(以下:PTT 角)の測定を行い、IFP の移動量を評価している。対象は健常 成人 25 人 50 膝である。エコー評価は、測定肢位を両膝関節 0°、45°、90°の 3 条件と し、PTT 角を各 3 回測定した。結果は、膝関節屈曲角度の増加に伴い PTT 角が鋭角にな った。また、3 回の測定における検者内信頼性はすべて 0.9 以上と極めて再現性が高い値を 示した。エコーによる PTT 角を求めることが可能であり、膝関節屈曲に伴い PTT 角の減 少は IFP の近位方向への移動量を反映している可能性が示された。
【コメント】
臨床上、膝関節疾患の中で IFP 由来の膝前面部痛を来たしている症例を多く経験します。 セラピストにとっては、IFP の動態を簡便に観察することができるエコーは必要なツールに なってきます。そこで本報告から膝関節屈曲運動時に PTT 角が鋭角になることで IFP が近 位方向へ移動している可能性が示唆されました。PTT 角を用い膝関節運動時の IFP の移動 量を数値化することによって健患側で比較が可能となり患者説明や病態考察などに役立つ と考えました。
文責:敷妙純平
伊藤芳章ら: 整形・災害外科 61(11):1473-1480, 2018
【内容】
人工股関節置換術の合併症の一つに脱臼があり,後方軟部組織の温存により hip stabilization として脱臼抵 抗性を高めることが期待できるが,周辺組織を熟知していなければ手術時操作で損傷してしまう可能性がある.
本論文では,解剖用屍体 20 股関節を用い,後方軟部組織の詳細や意義,実際について報告されていた.
大腿骨大転子内側面において,内閉鎖筋と上・下双子筋の付着部は接しており conjoined tendon を形成し, 短外旋筋群の中では最も前方に付着していた.梨状筋は conjoined tendon 付着部より後上方の大転子頂部 近くに付着し,外閉鎖筋は conjoined tendon 付着部と接することなく,その後下方にある骨性のくぼみに単独 で付着していた.関節包は conjoined tendon 付着部と外閉鎖筋付着部に近接して付着しており,前方が厚く, 後方の外閉鎖筋付着部近くでは薄い膜状になっていた. 股関節屈曲時における筋の走行や作用から,短外旋筋群の中では外閉鎖筋が最も外旋作用に働きやすいこと が推察され,THA 術後の脱臼予防として内旋制動性を有する筋ではないかと報告されていた.
【コメント】
本論文は,短外旋筋群や関節包付着部の詳細解剖について述べられていた.
外閉鎖筋は最も外旋作用に働きやすく,THA 術後の脱臼予防として内旋制動性を有すことが分かった.
我々,理学療法士は,脱臼予防として外閉鎖筋の収縮誘導が治療の一助となるではないかと考えた.術式に関わる筋や関節包,神経の走行や作用等の詳細解剖について理解を深めることや,術者との情報共有 が重要であることを再認識することができた.
文責:舘英里
臼井要介ら:日本臨床麻酔学会誌 Vol.38 No.1,128〜128,2018
【内容】
超音波ガイド下神経ブロックの進歩により,運動機能を温存し,知覚だけをブロックする工夫が進んでいる。手指の運動機能再建術において,知覚神経だけに局所麻酔薬を作用させて行われるWide Awake Hand Surgery(WAHS)は,手術中に再建筋と拮抗筋の適切な筋緊張を残しながら運動機能が把握できる。
本報告では、手指の各筋肉の役割と支配神経の分岐パターンが整理され、固有示指伸筋腱を用いた母指伸展再建術など,手背から前腕背側のみに侵襲のある術式におけるWAHSに必要な4つの末梢神経ブロック(後前腕皮神経,橈骨神経浅枝,尺骨神経手背枝,および筋皮神経)について超音波画像も併せて説明されている。
運動機能解剖学と超音波解剖学の知識と正確な選択的神経ブロックの技術は、WAHSの麻酔だけでなく運動器の侵害受容性疼痛の診断と治療を行う上でも重要だと思われる。
【コメント】
患者の症状を理解するためのポイントとして末梢神経の障害に注目することも重要となる。末梢神経障害を評価するためには支配する筋の筋力、支配領域における表在感覚、神経の走行・分岐パターンの解剖などについて理解することが重要である。
今回の報告ではWAHSを行う中で各筋肉の役割と支配神経の分岐パターンを理解することで必要な末梢神経ブロックを決定できることが紹介されていた。
これらの知識は我々理学療法士が理学療法を行う際にも症状を解釈し治療へ繋げるため にも応用できると考える。症状の出ている部位を詳細に確認(各神経の支配領域の表在感覚、筋肉一つ一つに対する筋力を評価)することで末梢神経障害の障害部位の特定が可能となる。
こういった正確な評価の重要性はこれまでにも学んできたはずだが、今一度詳細な評価 をすることの重要性を再確認することが出来た。
近年、理学療法士の臨床現場でも超音波画像装置を導入できる現場が増加しており、超音波画像装置の活用も末梢神経障害の障害部位を特定するための強い味方となり、治療の幅を広げることも可能だと考えられる。
文責:永田 敏貢
工藤陽平ら:脊髄外科 23(1)19‐23. 2009
April 30,2021
【内容】
絞扼性尺骨神経障害の好発部位としては、①尺側手根屈筋の二頭間、②肘部管、③上腕骨内側上顆、④筋間中隔、⑤arcade of Struthersの5つが主に考えられている。
本報告では、主に肘部管症候群の手術症例51例の尺骨神経の責任絞扼部位とその頻度、手術方法についての検討を行っている。
結果は、責任絞扼部位は単一であることが少なく、①尺側手根屈筋の二頭間40例、②肘部管38例、③上腕骨内側上顆8例、④筋間中隔1例、⑤arcade of Struthers 1例と、①と②での絞扼頻度が特に高いことが報告されていた。また上記の絞扼部位に当てはまらない症例が7例が存在しており、滑車上肘筋による圧迫、神経外ガングリオン各2例、神経幹内ガングリオン、異常血管による絞扼、脱転した関節軟骨による圧迫各1例が存在していた。責任絞扼部位の判定には、術前にTinel兆候と神経伝導速度(インチング法)を用いて評価しており、術中に確認できた絞扼部位ともほぼ一致していたとされている。
手術方法に関しては、単純絞扼例においては神経剥離術が、尺骨神経亜脱臼を伴った絞扼例においては神経移行術が望ましいとの見解であった。
【コメント】
今回の報告から肘部管症候群の症例においては、肘部管での評価に加え、尺側手根屈筋の二頭間、上腕骨内側上顆、筋間中隔、arcade of Struthers等の近隣の絞扼部位に関しても確認していく必要があると感じました。特に尺側手根屈筋の上腕骨頭と尺骨頭の筋間に関しては、肘部管と比較しても絞扼されている可能性が非常に高いため、尺側手根屈筋自体や、二頭間の状態を確実に捉えることができる評価および触診技術も必要になってくると思われます。絞扼部位によってはアプローチ内容にも大きく違いが出ることが考えられるため、治療効果を出していくためには、確実な絞扼部位の把握、評価、それに伴った運動療法が非常に大切になると実感しました。
文責:石丸 栄大
※この文献はGoogle ScholarにてFreeでダウンロード可能です。
March 31,2021
【内容】
新鮮凍結標本18肢(右10肢 左8肢)を使用し、腋窩から尺骨神経を遠位へ解剖し、上腕三頭筋内側頭との関係性を調べるため詳細解剖を行いました.結果は、18肢のうち17肢で尺骨神経が、上腕三頭筋内側頭へ分岐していました.このうち11肢は、尺骨神経から直接分岐しており、残りの6肢は腋窩レベルで橈骨神経から分岐する橈骨神経尺骨神経枝(The ulnar collateral branch of the radial nerve)から上腕三頭筋内側頭へ分岐していました.橈骨神経尺骨神経枝は、これまでの解剖研究では認識されていなかった神経で、腋窩レベルで分岐した後は、尺骨神経とともに並走していきました.
【コメント】
上腕三頭筋内側頭は、一部尺骨神経の支配も受けていることが分かりました.投球動作における上腕三頭筋内側頭は、肘関節外反・屈曲制動に働く重要な筋肉であり、繰り返しの屈曲・外反ストレスは、上腕三頭筋内側頭のSpasmを生じさせ、尺骨神経症状を惹起するという報告がされています.今回の論文から、尺骨神経の伸張ストレス自体が、直接的に神経支配を受けている上腕三頭筋内側頭に影響を与え、容易にSpasmが起こることも想像できます.
病態を理解する上で、筋Spasmは神経症状の原因なのか、結果的に起こっている現象なのかは、今後考える必要があると感じました.神経の詳細解剖を理解する重要性を再確認することができました.
文責:宮地 晴佳
February 28,2021
【内容】
本研究の目的は三角筋下滑液包にゼラチンを注入した後、滑液包のメゾスコピック解剖と、滑液包に走行する感覚神経の分布を特定することである。韓国人新鮮遺体11名(平均年齢65歳、43-88歳)の18肩を解剖した。矢状面より上腕骨大結節の最も膨隆した点を基準点(GT)とし、GTを通る水平線をx軸、GTが通る垂直線をy軸とした。結果:三角筋下滑液包の範囲はGTの前方、後方、上方、および下方の平均距離とし、それぞれ1.9±0.6、2.4±1.3、2.1±0.7、および3.2±1.5cmであった。また、三角筋下滑液包に走行する感覚神経の分布に関しては18肩のうち15肩が腋窩神経の前枝に由来した。また、18肩のうち2肩が腕神経叢の後索が分布していた。さらに18肩のうち1肩は腋窩神経と腕神経叢の後索からの枝の両方が分布していた。本研究結果より、腕神経叢の後索が三角筋下滑液包を支配している可能性があることが示唆された。
【コメント】
本論文は三角筋下滑液包の詳細解剖と感覚神経分布を研究したものである。
本研究結果より、三角筋下滑液包は多くが腋窩神経支配を受けており、なかには腕神経叢の後索からの枝が分布している場合や、その両者が分布している場合があることが分かった。
先月の宇野先生の報告より、肩峰下滑液包にも腋窩神経が分布していたことも踏まえ、肩関節疾患における腋窩神経の影響は必ず確認するべきであることが再確認させられた。
また、肩関節周囲の末梢神経は腋窩神経以外にも多く存在するため、それぞれの神経の解剖、走行を理解し、病態考察に落とし込んでいくことで、正確な疼痛解釈ができる可能性が向上すると考える。今後も、末梢神経の理解を深めるための努力を続けていきたい。
文責:藤尾 隆司
February 24,2021
【内容】
日本人成人遺体10名(男性:8体 女性:2体)の20肩を解剖し、肩関節周囲組織に分布する腋窩神経の枝を解剖しました。結果は、20肩のうち12肩は腋窩神経の前枝が肩峰下滑液包に分布していました。さらに20肩のうち8肩は上腕二頭筋長頭腱周囲に分布していました。これまで上腕近位外側部痛や前方部痛は肩甲上神経によるものと考えられていましたが、腋窩神経が痛みに関与している可能性が示唆されました。
【コメント】
本論文は腋窩神経の詳細解剖を研究したものです。
本研究結果より、腋窩神経が三角筋や小円筋だけでなく、肩峰下滑液包にまで分布していることが重要であると考えます。腋窩神経は上腕近位外側部の感覚を支配しています。腱板損傷や投球障害肩などの肩峰下インピンジメントにより肩峰下滑液包炎を惹起した場合、上腕近位外側部に放散痛として生じることが予測できます。また、肩峰下滑液包炎により棘上筋と肩峰下滑液包との癒着を生じるとの報告もあることから、夜間痛や結帯動作に伴う上腕近位外側部痛も腋窩神経由来の疼痛と考えることもできます。
支配神経の詳細解剖を理解することができれば、動作に伴う疼痛解釈の可能性が広がります。今後とも末梢神経の勉強を進めようと感じました。
文責:宇野 幸一
M. S. Ballal,C.R. Walker,A. P. Molloy:The anatomical footprint of the Achilles tendon. THE BONE & JOINT JOURNAL pp.1344-1348.(2014)
November 30, 2020
M. S. Ballal, C. R. Walker, A. P. Molloy : The anatomical footprint of the Achilles tendon. THE BONE & JOINT JOURNAL pp.1344-1348.(2014)
【内容】
新鮮凍結標本12体を用いて、アキレス腱の踵骨付着部の解剖を行いました。さらに防腐処理された10体を用いて後踵骨滑液包について調査しました。腓腹筋内側頭は踵骨結節の下面に停止します。ヒラメ筋は踵骨結節の中面かつ内側に停止します。腓腹筋外側頭は踵骨結節の中面かつ外側に停止します。後踵骨滑液包は、22献体のうち15献体に二区画存在していました。これらの新しい観察は、下腿三頭筋及び後踵骨滑液包の機能を理解する上で必要な知識になります。
【コメント】
本論文は、アキレス腱の踵骨付着部について詳細な解剖研究を行ったものです。
腓腹筋内側頭・腓腹筋外側頭・ヒラメ筋は、近位から遠位へと走行する際にねじれ構造を成しているため、起始部と停止部の配列が異なります。また踵骨結節への停止は一塊ではなく、各facetへと付着します。この構造は棘上筋・棘下筋・小円筋が上腕骨大結節の各facetへと停止する構造と似ています。踵骨結節の圧痛所見の有無を確認する際には、踵骨結節のどのfacetに圧痛を認めるかを詳細に評価し、病態解釈及び運動療法に活かすことが重要です。また、後踵骨滑液包のチャンバー(区画)についても分かれるものと分かれないものとがあることを説明しています。アキレス腱停止部の圧痛所見を得る際には、是非参考にしていただきたい情報です。
フリーダウンロード可能で、詳細な解剖写真と共に記述された論文ですので、是非ご一読ください。
文責:久保田大夢
ACL再建術のハムストリング腱自家移植による伏在神経膝蓋下枝の損傷 斜め切開と垂直切開の比較
November 08, 2020
Injury to the Infrapatellar Branch of the Saphenous Nerve during ACL Reconstruction with Hamstring Tendon Autograft: A Comparison between Oblique and Vertical Incisions Arch Bone Jt Surg2018 Jan; 6(1): 52–56.
ハムストリング腱自家移植による関節鏡視下ACL再建術の際のハムストリング腱採取による伏在神経膝蓋下枝(IPBSN)損傷は、症例の最大86%で報告されている。膝前部の痛み、知覚異常、痛みを伴う神経腫瘍、さらには交感神経性ジストロフィーが発生する可能性がある。これらの合併症は、手術による患者の満足度に影響を与える可能性がある。
IPBSNと鵞足との密接な関係を考慮すると、神経損傷の完全な予防は不可能であるように思われる。膝の内側のIPSBNは、膝前面で遠位外側に約45°の方向に走行している。したがって著者は、神経損傷の可能性はIPBSNと平行して皮膚を切開することで減少する可能性があると考えた。この研究では、IPSBN損傷を垂直切開群と斜めの切開群を比較した。
結果は感覚喪失領域と痺れの訴えの両方で斜め切開群が優位に減少した。
IPSBNは膝の内側で鵞足と親密な位置関係がある。さらに、膝蓋骨の下極から遠位脛骨結節までのIPBSNの横枝には多くのバリエーションがある。したがって、腱を採取するために皮膚を切開すると、神経損傷は避けられない。しかし、神経通路に平行な切開は、神経損傷を少なくする可能性がある。
この研究は、斜めの切開が従来の垂直の切開と比較してIPBSN損傷を大幅に減少させ、患者の不満を減少させる可能性があることを示唆している。
手術による神経損傷に対して理学療法士が手を加えることは出来ないが、皮切と神経の走行の関係を見ると、術後の癒着予防を十分に行わないとIPSBNの症状が出てしまうことがあるのではないかと感じた。
ACL再建術(STG法)の運動療法をする際は気をつけたい。
文責:渡辺将志
超音波画像診断装置を用いた内転筋管の位置について
September 30, 2020
Defining the Location of the Adductor Canal Using Ultrasound
Regional Anesthesia and Pain Medicine 42(2)241-245.2017
臨床上、TKA後の膝痛に対して麻酔科医が内転筋管ブロック(伏在神経ブロック)を実施し鎮痛を図ることがある。内転筋管ブロックを行うランドマークとして上前腸骨棘と膝蓋骨を結んだ中点(以下:大腿中央)に注射することが多い。しかし、実際は大腿三角ブロック(大腿神経内側広筋枝など)をしている可能性がある。そのため、本論文の目的は、超音波診断装置(以下:US)を用いて内転筋管の正確な位置を特定することとした。なお本文献の大腿三角は鼠経靭帯、縫工筋の内側縁、長内転筋の内側縁で構成される三角形を大腿三角としている。
対象は健常人22名である。方法は、はじめに大腿中央の皮膚上にマークした。USを用いて鼠径部レベルの大腿動脈を描出して遠位に追っていき、内転筋管の近位端と遠位端を特定し、皮膚上にマークした。内転筋管の近位端は、縫工筋の内側縁と長内転筋の内側縁が画面上で一致した点とした。遠位端は、大腿動脈が縫工筋から深層にある内転筋裂孔へ入り込む点とした。測定項目は大腿中央から内転筋管の近位端までの距離とした。
結果は、大腿中央から平均4.6㎝遠位に内転筋管の近位端が存在していた。また、遺体解剖を用いた研究においても同様な結果が報告されている。そのため、USにおいて内転筋管を正確な位置を特定することは可能である。また、大腿中央をランドマークにしたブロック注射は、内転筋管ブロックではなく、大腿三角ブロックである可能性が示唆された。
この報告を参考にすると、内転筋管または伏在神経の圧痛所見の精度を高めることができると考える。内転筋管の位置は、大腿中央から平均4.6㎝遠位にあり触診する上で大まかなランドマークになる。それに加え、長内転筋内側縁、縫工筋内側縁の正確な触診技術があれば内転筋管の近位端をより正確に確認できると考える。
そのため、整形外科リハビリテーション学会で大切にしている「正確な触診技術」が改めて重要と感じた。また、USは、触診の正確性を確認するのに必要なツールになるため、ランドマークを参考に描出するとより正確な所見が取れると考える。
文責:敷妙純平
伏在神経膝蓋下枝の走行について
August 28, 2020
松永和剛ら:伏在神経膝蓋下枝の走行について
整形外科と災害外科46: (3) 838~840,1997.
本文献では、大腿遠位内側で内転筋管(Hunter管)を出た膝蓋下枝が皮下に出るまでの走行と縫工筋の関係が調べられた。
下枝の走行を追求できた35肢と切断肢1肢の計36肢を用いた結果、伏在神経膝蓋下枝が縫工筋後縁を回り、筋表面を前方に向かうもの15肢(41.7%)、縫工筋筋腹を貫通して筋表面を前方に走るもの19肢(52.8%)、2本に分岐しレベルを違えて2本共に筋腹を貫通し筋表面を前方に走るもの1肢(2.8%)、2本に分岐し1本は筋腹を貫通し、他は筋後縁を回って筋表面に出るもの1肢(2.8%)であったと報告されている。
この報告から、伏在神経膝蓋下枝の約半数が縫工筋の筋腹を貫通しており、縫工筋の緊張が神経に影響を与えることが示唆された。
伏在神経障害は膝OAやTKA術後、膝関節鏡視下手術後などに生じることが報告されているが、膝内側や前面の疼痛、知覚障害に対し縫工筋による伏在神経膝蓋下枝の絞扼性障害も念頭に置き評価・治療を行う必要があると考えられる。
文責:苅谷賢二
*この文献はJ-Stageにてfreeでダウンロード可能です
股関節前面の関節包の解剖学的特徴について
July 26, 2020
吉田大地ら:外側広筋と股関節前面の関節包との付着について
久留米大学医学部解剖学講座 久留米醫學會雜誌 82(1/2): 26-33, 2019,02
外側広筋の起始は,一般的に大腿骨粗線外側唇・上方は大転子の下部から起始し,共同腱へ移行後膝蓋骨を介して脛骨粗面に停止すると報告されている.
今回の吉田らの報告では, 御遺体20体の内4肢(全体の20%)に外側広筋が股関節の関節包から起始している所見が確認された.
また,外側広筋が関節包へ付着していた群としていない群とに分け,「左右の棘果長・転子果長・大腿長・膝蓋骨直上・膝蓋骨10cm上方の大腿周径」を測定し,関節包に付着していた群の方が,「左右膝蓋骨直上の大腿周径が細く,大腿直筋の起始の面積は狭かった」と報告されていた.吉田らは,大腿直筋の起始部の面積が狭い部位を外側広筋が付着することで股関節伸展機能の補完効果があるのではないかと考察されていた.
この報告から,股関節前面の関節包には大腿直筋・小殿筋だけではなく、約20%の割合で外側広筋が付着するパターンが存在することが分かった.股関節前面の関節包に付着することから股関節炎患者や,人工股関節全置換術患者(特に前方アプローチ法)に対し考慮すべき筋であると考える.また, 外側広筋について大腿二頭筋や腸脛靭帯との筋間等の大腿後外側へのアプローチは多く紹介されているが,前方関節包への配慮も必要であると考える.
文責:舘英里
坐骨神経から分岐する筋枝の解剖学的な特徴について
June 01, 2020
深澤幹典ら:ヒト下肢の「ねじれ」についての肉眼解剖学的考察―坐骨神経から大腿屈筋への筋枝の特徴が示すこと― .第10回臨床解剖研究会記録.22-23,2006
坐骨神経は人体最大の神経であり膝の下方へと走行している。大腿の屈筋群へ筋枝を送っており、その分岐形態は多様だと報告されている。
今回の深澤らの報告では29体46側の御遺体について坐骨神経とそこから分岐する筋枝について起始、走行、分布が詳細に観察された。
そして、人の下肢は発生段階で内旋(ねじれ)を生じており坐骨神経の総腓骨神経成分、脛骨神経成分からの筋枝は近位から遠位に向かって内旋方向に変化する形態形成的特徴があり、ヒト下肢の発生段階におけるねじれを投影していると考察されていた。
この報告から坐骨神経の総腓骨神経成分と脛骨神経成分から分岐する筋枝は内旋の方向へ分岐していることが理解できた。神経の詳細な走行を知ることは超音波画像にて神経を確認する際にも活用することができる。
また神経の走行や筋枝への分岐部、分岐する方向などの特徴を知ることは理学療法における関節操作に活用することもできる。最近では末梢神経の走行に沿ったハイドロリリースなどが行われることが臨床的にも多くなっている。神経の走行を理解することは我々が理学療法を行う上でも重要だと思われる。
文責:永田敏貢
May 13, 2020
これからこのページにスポ支部スタッフが読んだ文献を紹介していきます!